
introduction

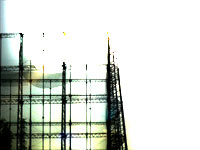

《終末世界》
驚愕。
明け方近く、
トランスレイトの家からアパートの自室に戻って来た馬数寄屋通(バスキヤ トーリ)は、
玄関前のドアを開け一歩室内に足を踏み入れた途端。
その思いもよらない光景に、長い前髪に隠れた瞳を見開いた。
玄関前に澱んでいた、日の光を知らない冷えた空気が、
ざわとトーリの首筋を舐めて広めのワンルームに侵入する。
生活感の無い、モノトーンで構成された部屋に散乱する衣類。
ヘリーハンセンのショートソックス、着古したネイビーのシャツ、
ダークグレーのボクサーショーツ、最近気に入りのトレーナー。
全て確か帰ってから洗おうと、脱衣籠に入れておいたものだ。
物盗りか?
一瞬そう思ったが、すっきりと配置されたクローゼットや引き出し類は整然とその姿を保ったままだ。
それに、
「…誰だ」
それに、何より。
「あ、はじめまして」
普段あまり使っていない声帯を震わせ、精一杯の威嚇を込めて言葉を紡ぐ。
頭の中の混乱が最高潮に達する。刃物を持っていたら握りしめて突きつけていたかもしれない。
「お前は、誰だ」
物盗りとはこんな風に、間の抜けた笑顔を浮かべるものだろうか。
「はじめまして、『もう一人の僕』」
その、散乱する服の上で青年は笑っていた。
タールのように黒い髪、日によく焼けた、鍛えあげられた褐色の肌。
体とは若干不釣合いな幼い顔付きをしているとは感じるものの、
別段変わった特徴のあるわけではない青年。
奇異なのはその、一糸纏わぬ姿くらいのものだ。
年の頃はトーリと同じか、二、三前後といったところだろう。
「へへ」
溌剌とした表情で、その青年は続けた。
「ごめんなさい、勝手に服散らかしちゃって。
ちょっと着るものが無くてさ、借りようと思ったんだけど…」
唾を呑む。青年の言い分を制止する。
「…待て、俺の質問に答えて、ない」
ばつが悪そうに頭を掻く青年に、
喉の異様な渇きを堪えながら、トーリは狼狽を悟られぬよう鋭く異議を唱えた。
服が無いとは妙なことを言う。
それじゃあこの男はこの部屋に来るまでどうしていたっていうんだ?
まさか裸で外を歩いていたとでもいうのか?
…いや、それよりもおかしいことがある。
トーリの部屋はアパートの二階だ。
アパートは国道から外れているとはいえ住宅街にあり、少ないとはいえ人通りもある。
部屋に入るには玄関を開けるか窓から忍び込む以外に方法は無いが、
自分はいつも外出前に部屋の鍵を閉めたかどうか確認している
(もちろん今日出る前もだ)し、玄関だってついぞ自分自身の手で
『鍵を回して、開けてから入った』ではないか。
そして窓は、
「ッ…!」
男の横を駆け足で通り抜け、木賊色の厚手のカーテンを引きちぎらんかの勢いで開け放つ。
トーリは目を見張った。窓は一枚たりとも割れていないし、
鍵もかかっている。
あと、駄目押しのようにこのアパートはオートロックだ。
それなら…
「お前は」
それなら、この男はどこから自分の部屋に入って来たんだ?
「僕はラング、『壁の向こう』から来たんだ。
…君に、忠告するためにね」
そう言って、褐色の肌を持つ青年は、再度人あたりのいい笑顔を浮かべた。
オーバーフラワー。一者セプトアギンタ。能力者。まがいものの世界。
魔弾の射手。日記。次々と消えていくパラレルワールドの『自分たち』。
どこからが君で、どこからが僕なのか。
●●たのは誰で、●●だのは誰なのか。
ほら、視えるだろう。
終末はそこまで迫っている。

《鏡像世界》
『私』はよく気を失う。
父さんたちは『私』は体が弱いから、と言う。
あの幼い頃の『事件』で、私の身体には常人では計り知れない負担がかかっているから、と。
けれど、本当にそうなのだろうか。
最近は特に気を失う頻度が高い。
『事件』からはもう、10年は経とうというのに。
大丈夫、私を信じなさいと父さんたちは言う。
でも、ごめんなさい。
もう、『私』は父さんたちを信じられません。
日も傾く準備を始めた午後4時過ぎ。
枷原造形大学のキャンパスは制作を終えた学生たちが続々と、
その点在する実習棟から姿を見せる影絵劇場になっていた。
秋の涼しげな、それでいてどこか照り返しの強い柿の実の匂いのする空の下を、
最先端を行き過ぎた感のある服装をした女学生やジャージ姿の男子学生が、
たわいも無い話をしながら校門へ向かって流れていく。
バスに乗って家に帰るもの、大学近くの下宿先へ徒歩で帰るもの。
そのまばらな人波の中を、彼と彼女は歩いていた。
彼と彼女は驚くほどよく似ていた。まるでそれは鏡のように。
『彼』は生成りのシャツにハイゲージのロングマフラーとジーンズ、
『彼女』はゆったりとしたニットの洋服にスカーフ、ロングスカートといった出で立ちの違いはあったが、
その顔はまったく同じ。コピーをとったように、同じだ。
彼は木米良カケル、20才。学生。
彼女は木米良ミチル、20才。学生。
二人は二卵性双生児である。
「よっ、ミチカケ」
校門に差し掛かった時、二人の背中を軽く押す手。
二人と同じCG科二回生、三黒江笑(ミクロエ エム)だ。
ダウンベストにカーゴパンツ。アッシュグレーの髪がよく似合うその顔は、少年のように幼く見える。
「エム」
二人は同時に振り返り、発声した。
「今日クラブ来いよ、俺VJするからさ」
そう誘うエムに、ミチルは可愛らしい笑みを浮かべる。
「あ、そうなんだ?」
でも、と申し訳なさそうに眉をハの字にし、
「ごめんね、今日は用事があって」
「用事?」
なんだよー、と不満そうなエムに、ミチルは桃色の唇で答えた。
「接待、かしらね」
嗤うように。
大学から徒歩10分ほどの閑静な住宅地の一角に、常人の感覚で言うなら「広大な」、
木米良兄弟の邸宅はあった。
厳(いかめ)しい青銅の門をくぐり、重厚なオークの玄関ドアをカケルが開ける。
「ただいま」
二人が帰宅を告げると、薄暗い廊下の奥、螺旋階段をゆっくりと降りてくる二つの影。
「おかえり、カケル」
「おかえり、ミチル」
もうひとつの鏡像。
影は初老の紳士、ミチルとカケルの父親「たち」。
二人はまったく同じダークカラーのセーターを着、まったく同じように白髪を後ろに撫で付け、
まったく同じ冷めた紅茶色の瞳で兄弟を階段の中程から見下ろしていた。
「ただいま、父さん」
その一卵性双生児の父親---俊樹と葉介---にもう一度帰宅を告げると、
ミチルはそのまま螺旋階段の横をすり抜けていった。
「啓吾さんから電話があったよ。
あと10分ほどで着くと」
「そう」
俊樹の言葉に、まるで興味が無さそうに答える。
「疲れちゃった」
休みたい、と暗に言うように、
ミチルはエントランスの中心に聳える階段の左奥に存在する自室に消えていった。
「…」
ドアの閉まる空虚な音を聴きながら、まだカケルは玄関にいた。
「カケル」
「…私も、部屋に」
「ああ」
階段の右奥にある自室に戻ろうと、
開け放たれたままの扉から茜色の光が射すそこをカケルが動こうとした時。
「…あ」
空気を切る気配。
「…着いたか」
「早いな」
エンジン音が、庭に鳴り響いた。
「こんにちは、カケル君」
「…こんにちは」
落ち着いた、品のいい背広を着た男性。
それが今、黒のマイバッハで庭に乗り付けたカスガイ新薬の次期社長、春日居啓吾だ。
社長というにはどこか精悍さが欠けているものの、その優しい面差しは見ているものを安心させる。
それは彼も同じで、普段温度を感じさせないカケルの顔が啓吾に会った途端、ほんの少し和らいだ。
「早かったですね」
「ああ、まずかったかな」
啓吾は申し訳無さそうに苦笑いを浮かべた。
「思ったより仕事が早く終わったんだ。それで…」
「あ、…いえ、そう言う意味で言った訳じゃ…」
柳眉をひそめ、運転席から視線をそらすカケルに、
「そうだ」
「え?」
思い出したように啓吾は背を向けると、後部座席に手を伸ばした。
何かをまさぐるような動作が数秒続いた後、
啓吾がウインドウからカケルに差し出したもの。
それは
「はい、これ」
「…あ…」
デルフィニウム、トルコキキョウ、ガーベラ、クジャクソウ、アレカヤシ。
綺麗な青いレースのリボンでまとめられた花束。
「飾っておいてくれるかい」
「…ありがとうございます、
父も喜ぶと思います」
抱える程の青い花束を胸に持ち、カケルは目を伏せた。
「勿論…ミチルも」
「よかった」
期待していた言葉に、啓吾は安堵の表情を見せた。
「中に入って下さい。父も挨拶を…」
ところがカケルがそう勧めた途端、啓吾は不思議そうな顔をする。
「いや、今日は…」
「え…?」
夕焼け、暗転。
「お待たせ、啓吾さん」
「…!」
細くしなやかな肉体を包む黒のクラシック・ドレス。
首を飾るプラチナのネックレスは知っている、啓吾がミチルにプレゼントしたものだ。
玄関から極上の夜を纏って現われたミチルに、カケルの動きが固まった。
「これから二人で夕食なんだよ。
ミチル君、言ってなかったのかい?
君も人が悪いな」
「ごめんなさい啓吾さん。
でも、言ったらカケルの機嫌が一日中悪くなると思って」
なるほど、と啓吾は微笑んだ。
「本当に妹思いだね、カケル君は」
「それじゃあ、夜には帰って来るわ。
行ってきます」
微笑を崩さぬまま、ミチルはカケルの肩に手を添える。
「…」
「…」
カケルは俯いて黙り込む。
その様を愛おしそうに、ミチルは猫のような目で嘗め回した。
「行ってきます」
「…」
囁き。
「どうしたの? 顔色が悪いよ」
囁き。
「やめて」
囁き。
「羨ましい?」
囁き。
「やめて」
囁き。
「羨ましいんだ」
囁き。
「やめて」
囁き。
「可哀想だね」
囁く。
「…」
残酷な。
「『ミチル』」
二人だけの囁き。
「…早く行け!」
微笑むミチル。青ざめた唇を噛み締めるカケル。
ああ、そこは鏡だらけの世界。
乱反射する鏡像に、
どちらが本物の私なのか、わからなくなる。
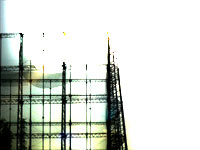
《解体世界》
西門判治(さいもん はんじ)は遅めの昼食を取るため、
大学から徒歩三分のカフェバー、『レッドアイ』で注文したオムライスが出来るのを待っていた。
茶系のインテリアでまとめられた店内で、その大柄な身体をスツールにちょこんと乗せ、
カウンターに毛深い肘を預けている。
「今日の午後はどうするの?」
一回生の頃から通っていたため、もう顔馴染みと言うより親友のような仲のレッドアイの店主、
座間味しのぶがチキンライスをフライパンで炒めながら聞いて来る。
「んー、どうしよっかなあ」
「もうすぐグループ展なんでしょ? エムから聞いたわよ」
「あ、一週間後」
「でも珍しいわよね、科が違う子同士のグループ展って」
「そうかな?」
一週間後に控えたグループ展、『bloom』に判治は参加する。
就職の内定も決まっていないのに、この時期にグループ展なんてどうかしてる。
そう同じ科の友人には笑われた。
どうかしてるかな、と判治は思う。
たまたま創りたいものがあって、ちょうどその時友人の三黒江エムから
今度知り合いと一緒にやるグループ展にお前も参加しないかと声をかけられた。
ごく自然な流れだと思うんだけど。
「今度は何を解体するの?」
オレンジ色に染まったチキンライスに半熟の卵をのせ、
ケチャップで可愛らしいハートマークを描くと
しのぶはそれを判治の前に差し出した。
「サービスね」と付け加え、サングリアを氷を入れたグラスに注ぐ。
「キリン」
「へえ、面白そうね。何が出てくるのかしら」
「そりゃまだヒミツ」
「楽しみにしてるわ」
判治は彫刻科の四回生。
何年も単位が足りずに留年しているため、大学内ではちょっとした有名人だ。
もっとも彼を有名たらしめている理由は、それ以外のいくつかの理由のほうだが。
そのうちのひとつが判治の創る作品で、一貫した特徴として
彼はまず大学内で巨大な石膏の彫像を作り、それを展覧会期内に会場で自ら『解体』する。
石膏でできたビーナス像を解体して現れる腐葉土とカブトムシの幼虫。
醜悪な怪物の像を解体して現れるカスミソウ。
ガラス細工、スパンコール、配線コード、携帯電話、瓶詰めのコーラ。
外見からは予想もつかないものが、判治の手にかかって解体された石膏像の中から姿を見せる。
そのパフォーマンスからついたあだ名は『解体屋』。
そしてもう一つのあだ名は
「ねえ、パンジー」
「ん?」
その名前と類人猿のような外見からつけられた愛称で、しのぶは判治の名を呼んだ。
「ちょっと話は変わるんだけどね」
オムライスを3分の2以上食べた判治の口元を、
「ケチャップついてる」
母親のようにペーパーナプキンで軽く拭ってやってから、
しのぶは判治に渡したものと同じサングリアを手元のグラスに注ぐと、
そのカシス色の液体を一口飲んでから話し出した。
「あの事件さ」
「あの事件?」
「今流行りの」
「…ああ」
そう言われて、思い当たる。
「連続首切り殺人」
こくりとしのぶは頷いて、迷惑そうに眉をひそめた。
「もう三ヶ月は経つわよ、その間に何人死んだと思う?」
「いや、僕んちテレビないし」
付け加えておくと新聞も読まない。
世俗の騒動には興味が無いのだ。
「昨日の死体で26人目だって。ほんと」
ごくり、と。
「警察はなにやってるのかしら」
しのぶは溜飲を下げるようにサングリアを飲み干した。
秋になったとは言え、昼下がりの青空はむう、と蒸すように判治には感じられた。
レッドアイを出た判治はつなぎの袖を腰元で巻くと、
大学に戻るか街に出るか考えていた。
丁度作品に使う材料が切れるか切れないか、といったところなのだ。
「どうするかなあ」
つなぎのポケットに手を突っ込み、ごそごそとまさぐる。
さっきランチの代金を払ったばかりの財布をそこから引き抜き中を覗く。
「うーん…」
昼は抜いてもよかったかな、と判治は後悔した。
仕方なく大学に戻ろうかと、足を大学のある坂の上に向けようとした時だった。
「おい、君」
「はい?」
坂の下から声がかかる。
そこには背広を着た、垢抜けない風体の大男が一人。
この天気で背広は暑そうだな、と判治は思った。
実際その男もそう思っているだろう。
その顔には大粒の汗が浮かんでは首筋を伝い、汚れの首輪のできた襟元に吸い込まれ続けている。
「この近くの住人か?」
「あなたは?」
「警察だ」
男は胸ポケットから黒い、縦長の手帳を取り出した。
その手帳には男の顔写真と『弟子屈 勝弥』の名前が記載されている。
テシカガカツヤ、とでも読むのだろうか。
「へえ、これが本物の警察手帳ですかあ。初めて見たなあ」
感心する判治に、男は困ったような視線を向けた。
薄汚れたつなぎを着た怪しい風体の男だと思って声をかけたものの、
あまりの邪気の無さに拍子抜けした、そんな表情だ。
「少し聞きたいことがあるんだが」
「はいはい、なんでしょう?」
「この辺りで不審な人物を見かけたことは?」
「不審?」
そうだなあ、と判治は顎に指を当てる。
自分もその中に含まれているかもしれない、なんて考えは髪の毛先程も無かった。
「うちの大学になら変人はいくらでもいるけど、
警察のお世話にならなきゃいけないような不審な人間はいないと思いますけども」
「君は大学生か?」
刑事、弟子屈はさらに目を丸くした。
それから自分の眼力も鈍ったものだと小さく溜息をつく。
「ええ、そこの枷原造形大の」
「…そうか」
「何か事件でも?」
「いや、それは…」
判治は眼鏡の奥のどんぐり眼で、弟子屈の顔を見上げる。
「連続首切り殺人事件?」
そう尋ねると、弟子屈はそれきり口をつぐんでしまった。
どうやら図星かな、と判治は思った。
「いやあ、大変ですねえ」
弟子屈はなんだかもう、早く話を切り上げたそうに額にその大きな手をあてる。
「君も大学の友人に注意するよう言っておいてくれ。
どうせ毎日夜遊びしてるんだろう」
「やだなあ、それ偏見ですよ。大学生が皆毎晩コンパしてるわけじゃないです。
ま、けど」
判治は弟子屈の顔をまじまじと見ると、屈託の無い笑顔を浮かべた。
「刑事さんみたいないい男とだったら夜遊びしてみたいですけど」
「な…ッ!?」
その不意をつく台詞に弟子屈の顔がみるみる紅潮していく。
「それは…その、何…どういう…ッ、いや、その…ッ!」
「わはははは」
狼狽という言葉がこれ以上というほどに似合う弟子屈を
悪戯が成功した子供のように眺めて、
「それじゃ。また会えるといいですね」
手を軽く二、三度振ると、判治は弟子屈に背を向け、大学へと続く坂を上って行った。
「…」
判治の去った後に生ぬるい風が吹く。
「…なんで、わかったんだ…?」
狐につままれたような顔で、弟子屈は奇妙な男の背中を見送った。
そして、世界は解体される。

戻る